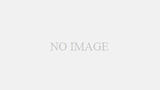宮沢賢治の雨ニモマケズに「一日ニ玄米四合ト味噌ト少シノ野菜ヲタベ」という一節がある。
質素な食事として受け取る人が多いと思うが、米100%の主食という点に注目すると、実はとても贅沢な食事なのだ。
賢治が雨ニモマケズを書いたのは1931年(昭和6年)である[1]人見千佐子『リアルなイーハトーヴ ―宮沢賢治が求めた空間―』新典社、2015年、p291 。
当時の米は農家にとって貴重な現金収入源だった。
そのため麦・雑穀・いも類・大根・大根の葉などを混ぜて節米し、販売にまわすのが普通だった。
現に賢治の故郷である花巻市のとなり、紫波町の日常食で当時一番多かったのは、冬が大根かて飯、春から秋は麦飯である[2]「日本の食生活全集 岩手」編集委員会『聞き書 岩手の食事』農山漁村文化協会、1984年、p137。。
花巻も似たような食事だったと判断していいだろう。
現金収入を得るために、賢治の周りの農家もそうやって必死に節米していたはずだ。
当時の農家にとって、米だけを主食にするのはたとえ玄米でも贅沢だったのである。
賢治が玄米とはいえ米だけの飯を食べられたのは、まわりの農家より米以外の現金収入が多かったということなのだろう。
以下は関連記事です。
下は宮沢賢治の故郷の近くで普通の農家が食べていた食事の再現。